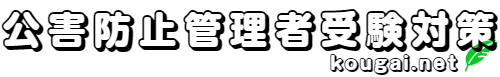瀬戸内海はいわゆる「閉鎖性水域」です。
このため、水質の汚れの影響を受けやすいです。
このため、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸内法)でほかの水域とは異なる扱いを受けていますし、総量削減規制(化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準)が定められています。
このことは私たち公害防止管理者にも大きな影響を与えています。
僕が勤務する工場でも、特に「リン」「窒素」などの富栄養化にかかわる物質については非常にシビアに処理、管理しています。公害防止管理者の試験でも富栄養化や栄養塩の除去については毎年出題されますよね。
このように、閉鎖性水域の栄養塩の問題は公害防止管理者にとって、非常に重要な問題なのです!!
公害防止管理者にとって気になるニュースが!!
最近、公害防止管理者にとって見逃せないニュースが流れてきました。
瀬戸内海「きれい過ぎ」是正 水域設け対策、漁業影響防ぐ―法改正へ・環境省 というニュースが飛び込んできたのです。
ニュースの内容はこうです。
瀬戸内海の一部で海藻類などの栄養源となる窒素やリンといった「栄養塩」の濃度が下がり、養殖ノリの色落ちや、漁獲量の減少が起きている事態を受け、環境省は対策を講じる方針を固めた。栄養塩を増やす水域を設定できる新制度を導入し、「きれいになり過ぎた」(同省幹部)状況を是正、漁業への影響を防ぐ(こちらのニュースより)。
確かに「海がきれいになりすぎて困る」という話を聞いたことがある
僕自身も、「海が奇麗になりすぎて魚が取れなくなった」などの話を地元の漁師さんから聞いたことがあります。確かに、栄養塩は生物にとって必須のものです。リンや窒素がなければ生き物は体を作ることが出来ません(私たち人間にとっても窒素とリンは大事です)。
だから、あまりにも栄養塩が少なくなると「漁獲量が少なくなる」というのは可能性としては十分ありうるわけです。
呉線に乗りました!車窓からの景色をご査収ください。 pic.twitter.com/Cx30SfzoKG
— めたのさえた(資格マニア家族) (@kougainet) September 28, 2020
この対策として、計画的に栄養塩を流す!?
この対策として、栄養塩を「計画的に流す」ことが提案されているようです。
記事には以下のようにありました。
赤潮の発生は激減したものの、近年は一部水域で養殖ノリやイカナゴ漁に悪影響が出ている。一方、ハマチやタイの養殖水域では、赤潮の防止で引き続き栄養塩の積極的な除去が必要だ。
このため、環境省は現行法の枠組みを維持しながら、新たに栄養塩を増やす水域を設定できるようにする考え。沿岸の府県や市町村は、濃度の目標値や計画を決めて対策を実施する。具体策としては、ノリの養殖が行われる秋ごろから翌春にかけて下水処理場の運用方法を調整し、排出する栄養塩を増やしたり、ダムやため池から放流して底にたまった泥から栄養塩を供給したりすることなどが考えられる。こうした取り組みは一部の自治体が既に実施している。新制度により、自治体がより対策を進めやすくし、各水域の状況に応じたきめ細かい対応を促す(こちらのニュースより)。
今まで、「悪者」のように扱われてきた栄養塩が見直されてきた。
このことは公害防止管理者の僕たちにとって非常に興味があるニュースではないでしょうか?
これからも、この動きに注目していきたいなぁと思っています。
家族で夜の海を見に来たよ! pic.twitter.com/xTEOJ7kmyp
— めたのさえた(資格マニア家族) (@kougainet) October 19, 2020
僕は瀬戸内海大好きですからね!