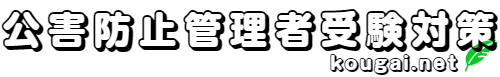2020年度(令和2年度)の公害防止管理者試験の体験談をまとめました。勉強をするときの参考にしてみてください。
騒音・振動体験談(フミさん)
(結果)
公害総論:水1・大気1を持っているので免除
騒音・振動概論:合格
騒音・振動特論:不合格
残念ではありますが 受験の時から危ないとは思ってました。
そのあたりはこれから説明するとして
(学習物)
・2017年度公害防止管理者等国家試験正解とヒント
(BOOKOFFで700円で買った中古)
・平成24年度 公害防止管理者等国家試験講習会 基礎講座(騒音・振動)
(Gooleで適当に検索かけて引っかかった資料もしかしたらもう拾えないかも)
・ONOSOKKI 騒音計の使い方
(騒音計で検索して引っかかった資料)
(勉強方法)
学習は9月前半から開始
環境計量士の騒音・振動持っているので 甘く構えてました。
やっぱり2カ月は見ておくべきでした。
学習物で役に立ったのは 検索で引っ掛けた講習会資料
初めからこれ見てればと 後悔するほどよくまとまってます。
(これやってれ全部理解すれば計算問題と愉説問題の5割はクリアしたも同然)
今、検索して落とせるなら今のうちに落としておきましょう。
あと騒音計はもっとしっかり覚えていればと
測定範囲と校正期間・器具の機能は覚えておきましょう。
過去問自体はどの年代でもいいんで正解とヒントを解いていれば、大丈夫だと思います(落ちた私は不十分だった)
いつもなら 何をどう覚えるみたいな書き方しますが、はっきり言って[24年度講習会資料] 数枚のプレゼン資料ですが、これがすべて +過去問だと思います。
さて、本来は合格して気持ちよく新年迎えたかったですが
来年へまた頑張るということで やっていこうと思います。
水質1種体験談(L.Cさん)
知り合いが水質処理の研究をしていたこと、会社で報奨金が出るため元々水質処理について体系的に学んでみたかったこともあり受験を決意。
化学系の知識は多少持っているため比較的とっつきやすかったのも後押ししてますね。
使用参考書
電話帳の最新版と問題集
公害防止管理者試験 重要問題集(三好康彦先生)が古本屋で安く売ってたので確認のために使用。
勉強法
勉強法は 公害防止ネットとレコメンタンクってところの体験談を参考に勉強してました。
勉強開始したのは7月からで、勉強した順番はブログなどを参考にとっつきやすそうな順番にしようとしました。
大規模水質 → 公害総論 → 水質概論 → 汚水処理特論 → 水質有害物質特論の順番にしました。
順番については、この順番で良かったと思います。 大規模は後に回してもいいと思いますけど。特に法律系が凄いとっつき悪いので総論や概論で枠組みを頭に入れていかないと全く意味不明です。初めて受験するなら公害総論と水質概論は、先に勉強されることをおススメします。
法律ができた背景や対象となる物質が頭に入るので、その後の汚水処理特論や水質有害物質特論で出てきた物質の内容が少し頭に入りやすくなると思います。
3か月あったのでじっくり勉強しようとして テキスト読む → 過去問の演習の順番でやってましたが、特に短期間で合格したい場合、正直これはオススメしません。
最初から公式問題集で過去問いきなりやって2~3周くらいガン回しして、問題の解説とか大体頭に入れてからテキスト読んだ方がいいです。
頻出箇所・重要箇所については解説も詳しく載っていますし、それを頭に入れてからテキストを読むとテストに出そうなポイントを中心に時間を無駄にかけずに読めると思います。問題集二冊使ってましたが、公式問題集がテキストと同じ表現使っている + 解説も詳しいので、それを中心に演習するのが一番いいと思いました。
公式問題集を10年分 解説の根拠も合わせて覚えていたら本試験でも4~5割はほぼ間違いなくとれるので、そういう意味でも公式問題集は少なくとも一冊は完璧にこなしておくことを強くお勧めします。
重要問題集は、使っている記号などが違ったりして紛らわしい + 解説が凄い簡素だったりで メインには使っていませんでしたが
出題頻度別に問題が並べてあって、苦手な箇所わかるので実力確認してテキストでその分野読みなおしたり、補強には凄く良い参考書でした。
問題集やブログを通じてかなり勉強しても事故りそうな科目があったので、そこを厚めに勉強することにしました。
優先順位としては
水質概論 >>>>> 水質有害物質特論 >>> 汚水処理特論 >> 公害総論 >>>>>>> 大規模水質特論
理由:
水質概論:
問題数が10問と少なく的が絞りにくく色んな範囲から出てくるため 年によって体感難易度が激変する科目。
特に水質汚濁防止法の誤りを選択する問題が連発されたらまず正解できない上に出る範囲も読み辛く、不合格に一気に近づく。
水質有害物質特論:
かなり細かい内容を問われる。分析が鬼畜で、とにかく一ページを理解する・覚えるのに時間がかかる。 他サイトのブログでも地獄と書かれていて100時間勉強したと書かれていたがやって納得。
汚水処理特論:
範囲が広い、装置関係は現物みたことないと意味不明。分析は鬼畜だが、有害物質より覚えやすいかな?個人的には。問題数が多く、計算問題が稼ぎやすい&最初の方の問題が常識でもとけるような問題が多く、過去問の演習中心で合格点だけなら取れる可能性高そうなので優先順位ちょい低め。
公害総論:
水質関係の問題の出題頻度が高く、環境基本法についてはめたのさえたさんの分析により、そこを押さえたらとれそうだったのと他科目との兼ね合いもあり優先順位低く設定。
大規模水質特論:
過去問見た感じあまり細かい部分まで問う問題が少なく、エスチャリー、海域系で細かい問題連打されない限り落ちそうになかったのと、この科目落ちたら他の科目落ちることだけは間違いないと思い優先順位はかなり低め。
次 各科目の勉強と勉強時間について
公害総論 30~40時間位?
実は凄い苦手意識強い科目(法律を覚えるのが凄い苦手なので)、とにかくとっつきが悪く環境基準、要監視項目などかなり紛らわしく最初全く頭に入ってこなかったこともあり、中々進まなかった科目。
進みが悪くかなり苦痛だったこともあり、水質概論と同時並行に勉強してました。
重複する内容も多かったため、少しずつ頭に入ってきました。水質の問題は、総論でも頻出のため水質関係の公害防止管理者を受験する場合その点でも有利ですね。
めたのさえたさんの環境基本法の出題傾向分析にはかなり助けられました。必敗パターンは 環境基本法で 細かい問題 or 新規問題連打 → 水質関連の問題がほぼ出ないですね。
水質概論 40時間位?
問題数が少なく出題傾向が一番読みにくく、細かい内容も出やすいため一番事故りやすいと感じた。恐怖の科目。化合物の毒性などは、比較的頭に入りやすかったのでそこを中心に頻出の環境基準達成率を中心に勉強に取れる問題を取りに行く戦略で勉強。
特に水質汚濁法の誤っている箇所連打 → エスチャリーなどの細かい問題は、必敗パターンなので当日でないことを願うばかり。
汚水処理特論 40~60時間位?
範囲が広く、とっつき悪い内容が多いですが(特に現物みたことないと意味不明な装置関係と、分析)、問題数が多くそこまで細かい問題が多くないため過去問の演習を中心に頻出箇所を押さえておけば、感で2択位まで絞れること、計算問題は解き方覚えれば稼ぎやすいこともあり、なんだかんだ受かりやすそうな印象。勉強時間的に分析法の細かいところまでは詰めることができず。
必敗パターンは、分析法の細かい問題と装置の細かい問題連打、計算ミスなどのケアレスミスですね。
それでも量が膨大なため、勉強時間は結構かかりましたが落ちたとしても完全に実力不足と納得できる科目で、分析系は過去問の知識勝負で半ば捨てて前半稼ぐ戦略で勝負。
8月は、工場が暑いこともありかなり消耗して集中して勉強できなかった方が悔やまれる科目。
水質有害物質特論 40~50時間位
しっかり整理して記憶しないと太刀打ちできない科目。最後3週間位しか勉強できなかったので、最初過去問とテキスト見た時かなり焦りました。
pHや使用する薬剤名など、しっかり記憶して処理プロセスの流れも理解してないと点数が取れないので、感でわからない問題を適当にマークして合格とかは一番起こりにくい科目だと思います(問題数の少ない概論や逆に問題数が多く取りこぼしが多くてもなんとかなる汚水処理で半分くらい解いて後、勘で6割ゲットはかなりありえますが)。ノートに書きながらしっかり細かい部分も覚えていって、何度も演習して無理やり頭につめこみました。
分析法の細かい問題までは覚えきる時間もなく、汚水処理などと混同してしまうと思い。これも過去問のみで、基本的な分析法の原理は覚えてノリで解くことに。 そのかわり、それ以外の部分はかなりしっかり覚えました。
この科目については、細かい部分まで詰めないと合格できないのでノートを自分で取り直すなどして整理することを強くお勧めします。
必敗パターンは、分析関係の細かい問題連打されるとかなり苦しいのでそれがこないことを願うばかり。
大規模水質特論 20~30時間位
ブログで見て簡単・簡単言われていたが、教科書を見て微分方程式と海域の水質処理の難解さに絶句。受験者は化け物かと思いましたが、過去問回して納得。確かにこりゃ簡単だわって思った科目。
とりあえず頭に入ってこない、海域系とエスチャリーなどの話は過去問頼みで後半の工場などの処理はテキストも読み込みました。
必敗パターンは、エスチャリー、大規模海域で気合の入った問題出されることくらい。
落ちたとしても他の科目もまず落ちること間違いないので優先順位は低め。
さて実際の結果というか感想ですけど
体感的な難易度としては 公害総論 >> 汚水処理特論 >> 水質有害物質特論 >> 水質概論 >= 大規模水質特論
ですね。
公害総論:
前日深夜まで勉強していたこともあり頭がまわらないまま総論へ、問題を見て何問か解いてるうちに例年より細かい問題連打されており焦ったこともあり少し目が覚める。
一番自信のない科目。一科目落ちるとしたら間違いなくこれだろうって思いました。
勉強の優先順位的に、汚水処理や有害物質の分析法 もっと詰めたかったので仮に試験延期でも結果は変わらんかったでしょうね。
こりゃ落ちてもしゃーないわって感じですね。勘で書いた問題が、何問かあってないと合格できないので手ごたえ全くなし。
水質概論 :
総論が思いのほか難しく、落ちたかな?と思って集中力が切れたのか 移動と睡眠不足の疲れが一気に出てきて眠くてしかたなかったですが、鬼門の概論の問題を確認。
数問解いて、もろたで工藤って叫びそうになりました。重箱の隅をつついたような問題や言葉遊びみたいな法律の問題もなく、6割下回ることはまずなさそうな出来に落ち着きを取り戻し、問題を速攻解いて軽く見直して速攻休むことに。
まさかの 概論でデレを見れると思いませんでした。
汚水処理特論 :
二番目に自信のない科目(自己採点で 自信ある問題が 15個なかったので)戦略として分析問題思いっきり捨てて前半で稼ぐっていう戦略通りには動けたので感触自体は悪くないのですが。
計算問題の解き方がとっさに思いつかず、予想外に時間ギリギリまでかかりました(汗)。
落ちたとしたら完全に勉強不足・実力不足と納得できるので後悔はないです。 しっかり対策すれば受かりやすい科目という印象は変わってないですし。
水質有害物質特論 :
見たことあるような問題ばかりで、10問弱解いた時点でプロジェクトXのテーマが流れ合格の手ごたえを掴めました。
過去問の演習、各物質の処理方法をしっかり覚えた成果が出せたかなって思います。。
大規模水質特論:
鬼門の概論と水質有害物質特論については、合格の手ごたえあったのと 例年一番簡単な大規模水質のみなので正直もう帰宅モードです。
安心はできないので、工場系の処理について細かい部分を少し詰めて少し確認はしておきました。
問題を見て数問解いて、エスチャリーや微分方程式で煙に巻くという非業の敗北パターンにならず、5分くらいで全問解いてこの科目は合格を確信。問題傾向は変わっていましたが、すぐ対応できたので、公式テキストを読んでいたのがよかったのかもしれません。
途中退室できないので一応見直しして、ゆっくり休むことに。
結果としては、感触はそれほど悪くなくて 3~5科目合格って感じで、総論だけ落ちる可能性は高いですけどダイオキシンも取得予定なので、受験してとってしまおうと思います。汚水落ちたら流石に凹みますけど。
試験については、途中退室もできないですし、試験が全部終わっても結果はいつ発表とか、大規模終わっても水質一種の科目はすべて終わりました みたいな説明もなく正直驚きました。
普通に次の科目がある方は~って 同じような説明してますし’(確かに大気1種を併願してるとそうなるんですけども)、他の試験だと 大体はっきりそういう説明あるので 初めて受験すると驚くかもしれません。
水質2種・3種併願受験体験談(りゅうさん)
【受験した試験種類】
水質2種、水質3種の併願受験
2017年 騒音振動 合格
2019年 水質4種 合格
水質4種合格済なので、水質2種は水質有害物質特論のみ受験
水質3種は大規模水質特論のみ受験
水質1種にしなかった理由は、2種3種受かったほうが会社からの奨励金が多く当たる為
【使用したテキスト】
正解とヒント4冊
水質有害物質特論は、おしょー様のまとめを活用しました。
勉強時間があまりとれず、本格的に勉強しだしたのが9月28日からでした(・・;)(おい←)
とりあえず過去問をやります
平成18年〜令和元年までの過去問解きました。
水質有害物質特論はおしょー様のまとめで、各物質の問題をまとめてやりました。
時間がないので、やれるだけやろうと思い、過去問14年分を水質有害は5周くらい、大規模は1周と少しやりました。
やはり有害に時間を多くつかいました。
試験開始は14時35分〜
午前中の間に受験会場につき、検温をして中に入ります。
その時リストバンドを渡され、腕にまいてないと受験できません。
試験開始まで約3時間、最終チェックをします。
、、、覚えきれない(・・;)
勉強が追いついてないまま水質有害物質、試験開始です。
頭の中がごちゃごちゃで整理されて
おらず「あ~これ何だっけ?」てやつばかりになってしまいました。
難易度的には普通だったと思います
完全に実力不足です。
15時25分 有害物質特論終了
、、、ギリギリセーフかアウトだなこりゃ
16時から別の教室で大規模水質特論があります。
急いで2階に移動
同じ建物なので3分ほどで到着
試験開始まで20分ほどあります
間に合ったー(・∀・)
少しでも多くテキストの内容詰め込みます。
16時大規模水質特論試験開始です。
、、、、??
は?すごく難しい(・・;)
今まで1番簡単されてた大規模水質特論
過去問やってても、すぐ合格点にいったはずなのに、、、
まともに分かる問題が3〜4問しかない
落ちたなこりゃ、、、そう思いました
16時35分試験終了
2科目しか受けてないのにクタクタです。
【結果】
水質2種
水質有害物質特論 8問正解で不合格
水質3種
大規模水質特論 6問正解で暫定合格
となりました。
水質有害物質特論は、完全に勉強不足でした
大規模は運に助けられた感じです
難しすぎだろ(・・;)
今回の結果により
水質3種水質4種が合格済となる見込みですので
水質5科目中4科目が永久免除となります。
あとの1科目 水質有害物質特論を次回、全力で取りに行きます←
本当は今回で水質の5科目終わらせて次回から大気やりたかったんですが落ちたので仕方ありません。
大規模水質特論は油断大敵です。
問題数少ないので、簡単なはずとなめてかかるとヤバイです。