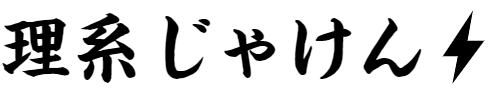生産技術、生産管理や経営工学およびQCの分野等で仕事をされた経験がある方は「QC7つ道具」をご存知のことと思います。その中でもパレート図は主な不具合の原因や内容を絞り込む手法として、非常に良く使用されるのではないかと思います。
今回の記事では、(1)QC7つ道具の一つであるパレート図の簡単な説明および(2)品質に関係ない普段の生活の中でQC7つ道具を使ってみると面白いという二つの話をしてみたいと思います。
QC7つ道具とは
「QC7つ道具」とは日本科学技術連盟(日科技連)が命名した呼び方だそうです。
QCサークルやTQCを企業等に導入、推進する際に、現場の人たちが使用し安い手法を選んで「QC7つ道具」というネーミングにして親しんでもらおうという意図だそうです。
QC7つ道具とは以下の7つです。
- パレート図
- 特性要因図
- 層別
- チェックシート
- ヒストグラム
- 散布図
- 管理図
全て、非常に重要な手法です。
今後ブログの中で紹介していくこともあると思います。QC7つ道具に関する本はたくさん出版されていますので参考にしてください。
パレート図とは
パレート図とは項目別の出現頻度の大きさを棒グラフの形で「大きい順」に並べるとともに、累積和を折れ線グラフで表した図のことです。
JIS Z 8101-2-1.19には以下のように解説されています。
項目別に層別して、出現頻度の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図。例えば、不適合品を不適合の内容の別に分類し、不適合品数の順に並べてパレート図を作ると不適合の重点順位がわかる(JIS Z 8101-2-1.19)。
少し、言葉では分かりにくいと思います。
それでは、簡単なパレート図を実際に作ってみましょう。
Aという製品の不具合内容を調査したところ、表1になりました。パレート図は全体の中で出現頻度の低い不具合内容は「その他」として扱います。ですので、以下の表の例で言いますと、「傷入り」「刻印漏れ」はその他として扱います。
「傷入り」と「刻印漏れ」をその他としたパレート図が表2です。

表2を使ってグラフを作成します。
すると下のパレート図を作成することが出来ました。

注目すべきは、上位の数項目(上のパレート図の例では2項目)が全体の80%以上を占めている点です。このようにパレート図を使用した品質改善活動では、上位80%の不具合内容や原因に絞り込んでいく作業に使用されることが多いです。
なお、パレート図を使用した「パレート分析」と調達の分野で使用される「ABC分析」は非常によく似た考え方です。ABC分析に関わる記事を以前書いていますので、興味がある方は参考にしてみてください。
⇒単に「買う」だけではダメ! 購買・調達担当者には【経営工学】を知ってほしい
品質に全く関係の無い普段の生活でもパレート分析してみると面白い(僕の海外渡航先の事例)
僕は経営工学の技術士です。
このような、経営工学やQC手法によって分析をする癖がついています(笑)。ですから、品質や生産管理にあまり関係のない分野でもパレート分析をしてしまうんですよね(笑)。
最近、僕は自分の海外渡航回数が50回を超えたことに気づきました。それで、「自分って国際人?」という風に思えてきました(笑)。それで、「国際人ならやっぱ英語でしょ」と思いTOEICやオンライン会話などを利用して英語の勉強をしています。
しかし、海外の渡航先をパレート分析してみた結果、
衝撃に事実に気づかされました!!
僕の海外渡航先のパレート図が以下です。

僕の渡航先は、
近場の「中国と韓国」で8割以上を占めているのです!
こうやって定量化して分析すると、僕は「国際人という感じとはちょっとちがっているなぁ」という印象を受けるのではないでしょうか? 「近場の中国によく行っている人という印象」に変わってくるのではないでしょうか?
勉強すべきは英語よりも「中国語」なのかもしれない
上記ようにパレート図を使用して分析すると、
- 僕のメイン渡航先が中国、韓国であること
- 英語より、中国語を必要とする機会が多いこと
が定量的にわかってきます。
つまり、英語を勉強するより中国語を勉強することが必要なのかもしれません。
実際、中国でビジネスをする際には英語を使用する機会はそれほど多くありません。ほとんど、たどたどしい中国語と「通訳さんに同行いただく」ことに頼って中国で仕事をしています。
ということは・・・客観的に考えると僕は、英語より中国語を勉強すべきという結論になります。
現在TOEIC900点を目指して勉強していますので、ここで英語の勉強をやめたくはありません。でもTOEIC900点取得後には少しずつ中国語の勉強をはじめらければなりません。
このような分析が客観的に出来るのが「パレート図」の面白いところです。
QC七つ道具は品質以外の分野でも使用できる!
このようにQC7つ道具を品質以外の分野や普段の生活に適用してみると、とても面白いと思います。客観的に物事を分析できます。特に技術者の皆さん、理系の皆さんはこのように普段からデータを使用して分析する癖がついていると思います。
仕事の分野だけではなくて、普段の生活でもQC手法を使用することで、どんな時でも「エンジニアマインド」をもった技術者になっていけると思います。是非試してみてくださいね。
「パレート分析の考え方を人生に当てはめてみよう」という趣旨の本も出版されているようです。
 |
リチャード・コッチ CCCメディアハウス 2018-08-30
売り上げランキング : 5408
|
【追記】公害防止管理者の区分別累計合格者数もパレート図にしてみました(笑)
公害防止管理者のホームページを制作していることもあって、2018年末現在までの公害防止管理者試験区分別合格者数をパレート図にしてみました(笑)!

この結果は「2018年の公害防止管理者試験の結果を徹底的に眺めてみたよ!!」にまとめています。興味がある方は参照してみてください。