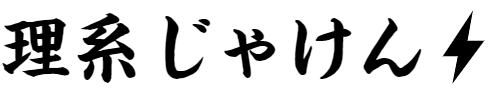今日はある技術士仲間から教えてもらったサービスを紹介したいと思います!
それが、超簡単に熱影響部最高硬さの予測が出来る無料サービスです。
このサービスは日本溶接協会が無料で提供しているものです。
溶接の熱影響部がどんな硬さになるかよそくすることができます。めっちゃ便利。日本溶接協会のホームページより。 https://t.co/T2uPKxBryv pic.twitter.com/QA6gz2eEH2
— めたのさえた(英会話×筋トレ) (@kougainet) June 16, 2020
本日はこのサービスについて紹介してみたいと思います。
溶接部は硬度が変化する
溶接部は温度が変化します。
というのも、通常金属には炭素(C)が含まれています。
そして、温度が非常に高くなります。
炭素以外の元素が溶接性に及ぼす影響(CrとかMoとか)海外で知らない材料に出会ったときでも書いた通り、炭素などの元素は溶接性に大きな影響を与えるんですよね。炭素以外の元素でも、以下のような元素は溶接性に大きな影響を与えます。
- C:炭素
- Si:シリコン
- Mn:マンガン
- Ni:ニッケル
- Cr:クロム
- Mo:モリブデン
- V:バナジウム
- B:ホウ素
- Cu:銅
そして、そのような変化は硬度の変化になって表れてくるのです。
一般的に、溶接部はまるで焼き入れの入ったような状態になり「硬度」が高くなっていくことが知られています。
そして、溶接後の金属の高度影響を与える因子として、以下のようなものが知られています。
- 溶接時の電流
- 電圧
- 溶接速度
- アーク熱効率
- 板厚
- 外気温度
- 予熱パス温度
- アークエネルギ
- 入熱量
- 溶接冷却時間
- 化学組成
ということはこれらの、因子がわかれば溶接後の高度が予測できるんです。
これらの因子を入力すると自動で予測硬度を算出
今回紹介する、無料サービスでは上記のような因子を入力すれば、自動的に予測硬度を算出してくれます。ぜひ活用してみてください。
とっても便利です。

僕はこのサービスをどのように使っているか
僕がこのサービスをどのように使っているかを紹介したいと思います。
溶接の専門家と議論するときに
僕は溶接の専門家ではありませせん。だから、あまり詳しいことは分かりません。
でも、溶接の条件や使用する溶接棒、材料の名前を教えてもらっておいて、
「この条件だと大体○○くらいの硬度になりそうですね」
などというと、
あ、こいつ、ある程度溶接がわかっているな
という目で見られます(笑)
ちょっとハッタリ?をかますのに便利です。
硬度を計測して、溶接品質が保たれているかチェック
硬度を計測すると、当初想定していた溶接条件が満たされているか、きちんとした材料が使われているか・・・など溶接品質を推定することができます。これは本当に助かります。
応力除去焼鈍(SR)をした時の効果に!
溶接後は応力除去焼きなまし(焼鈍)の熱処理をすることが多いです。
この目的としては、
- 残留応力の除去
- 割れを防止する
などがあります。
そして、この熱処理が適正に実施されていれば、いったん固くなった硬度が下がります。
つまり、適正に熱処理がなされているかどうかを確認するために、熱処理後に硬度を計ってみるということも一般的に行われています。
熱処理後には計算された硬度よりも下がっているかどうか確認することで、熱処理が適正に施工されているか確認することができます。
こういうときにも溶接後の理論硬度を把握していると非常に助かります!!
海外で聞いたことのない材料に出会っても安心!
海外では聞いたことがないような材料に出会うことがあります(【超便利!?】中国GB規格の鉄鋼材料の寸法と公差を調べられるサイトまとめ)。
そんな時でも安心です。
海外で聞いたことがない材料に出会った場合。
そしてそれを溶接していいかどうか、判断に迷った場合、僕は以下のプロセスで溶接可否を判断しています。
- まずはミルシートを確認して材料の化学成分含有割合を調べる。
- CeqとPCMを計算する(こちらを参照)
- その大きさによって溶接してよいかどうか判断する
- さらに、適正に溶接されたかどうか硬度から判断する
というプロセスで、溶接をある程度簡単に評価することができます。
是非、試してみてください。
僕は溶接の素人です(念のため)
一応念のためですが・・・僕は溶接の素人です。
この記事では僕が業務を通じて学んできたことを簡単に書いたつもりです。
ただ、素人なので記載内容にミスがあるかもしません。
気づかれた方は遠慮なく教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
| 図解入門現場で役立つ溶接の知識と技術 (How‐nual Visual Text Book) | ||||
|